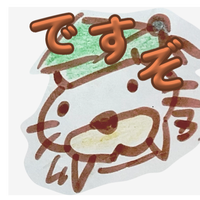こんにちは!
1級FP技能士のアシまるくんです!
おかげさまで記念すべき10本目の記事となりました。
第0章『真夏の天使と在りし夏』
皆様、"大好き!五つ子"というドラマをご存じでしょうか?
私が小学生くらいの頃、夏休みに、"笑っていいとも!"の後に放送されていた30分ドラマで、まさに夏休みの代名詞と言っても過言ではないそんな昼ドラマです。
10年近く続いた人気シリーズですが、そんな中で非常に印象に残っている場面(*1)があります。それは主人公の五つ子の一人、紀香が"英語が好きだからアメリカに留学したい!"というのに対し、知人のマイケルが"アメリカで何を勉強するの?"と尋ねる場面。さらに続けて、"留学は、英語を勉強するのではなく、英語で勉強するものだよ。"と助言します。
当時、確か私は中学生だった気がしますが、妙に衝撃を受けたような記憶があります。
(*1)20年近く前なので、当然に記憶が朧気なのはご容赦ください。ちなみに、マイケル役を演じたのは、パックンマックンのパックンことパトリック・ハーラン氏です。お笑いをやったり、ハーバード大学卒業だったり、役者業や、プレバト!!では俳句も嗜むなど、多彩な方ですね。
第1章『プログラミングを学ぶ子供たち』
2020年度から小学校で"プログラミング"を学ぶことになったというニュースは、記憶に新しいのではないでしょうか?よく考えずに、そのニュースだけを聞くと『今の子どもは小学生からプログラミングを勉強してすごい!』、『今後、プログラミングネイティブな子たちと同じ社会で競わないといけないなんて戦々恐々の思いだ。』なんて言う思いを生むかもしれません。しかし、こういったニュースに関しては、"実際に彼らが何を学んでいるか"ということに注目する姿勢がとても大切です。
新教育指導要領のポイント集 にも記載がある通り、小学生で学ぶプログラミングで身に着ける能力は"プログラミング的思考"です。
小学生やC言語やPythonなどを使って、ゴリゴリにプログラムを書いているわけではなく、"一つ一つの動きを組み合わせて、意図する動きを実現する論理的思考力"、まるでドミノ倒しのような感覚を養うのが小学校における到達目標です。
これは前章の言葉を用いると、"プログラミングを学ぶ"というよりも将来、"プログラミングで物事を解決できるように学ぶ"という言葉が適切なように感じます。
第2章『子供たちが触れているもの』
前章を踏まえて、実際に小学生がプログラミング教育の一環として触れているもので、私自身が体験したことがあるものを二つ紹介します。
一つ目は、"Scratch”です。
こちらは、ボランティアで小学生とかかわる機会をいただいたときに、実際に触っている様子を見せていただきました。こちらは"ビジュアルプログラミング言語"と言い、「動かす」、「回す」などの具体的な指示を組み合わせて、キャラクターをいろいろと動かすことのできるものです。私の小学生時代にこれがあったとしたら、おそらく私もそうしたでしょうが、さすが小学生。100回回すとか、同じキャラクターをコピーしまくるとか、まさにカオスというのにふさわしいやりたい放題なプログラムを書いていました笑
シンプルな指示を組み合わせて、キャラクターを思いのままに動かすというコンセプトは分かりやすく、プログラミング全くの未経験の大人が初めに触ってみるのも面白いのではないか、と思います。
二つ目は、"アルゴロジック"です。
こちらは、日本武道館の近くにある"科学技術館"に夫婦で行ったときに体験しました。プログラミングを体験できるパズルゲームです。夫婦で、片方はプログラミング経験者、もう片方は全くの未経験で挑みましたが、難易度の幅(*2)が非常に広く、二人とも楽しめるゲームでした。また、何人かのお子様がそのゲームを体験されていましたが、試行錯誤を繰り返しながら攻略しようとする姿が印象的でした。
(*2)ちなみに、そのあとスマホでできることを知り、1週間程度かけて全クリを試みました。全ステージクリアはできましたが、完全クリア(全ステージを最短手順でのクリア)はかなり難しく、途中であきらめてしまいました。
第3章『AIと共存する時代で子供たちは何を学ぶのか』
さて、いまや大人の学習にとっても、効率よく学習を進めるためにAIを活用することは必要不可欠と言っても過言ではないでしょう。
大人の学習ですらそうなのですから、"勉強することが仕事"とも言える子供たちの学習現場にAIが登場していることは言うまでもありません。まだ学校の教育の現場に登場するには至っていないはずですが、皆様ご存じ"進研ゼミ"なんかは当然のごとく、AIによる学習支援をしています。
しかし、これは"AIで学ぶ"事例ですね。"AIを学ぶ"とはどういうことでしょうか?
プログラミングのように楽しく学べればいいのですが、そうは問屋が卸しません。AIは比較的簡単に使えるにもかかわらず、リスクが大きいのです。どちらかというと、SNSに近いです。国もそんなことは織り込み済みでしょう、文部科学省から割と最近にガイドライン が出ています。小学生だけでなく、教員もまだよくAIのことを分かっていないので、まずは、教員からしっかりと身の守り方を伝えていこう、ということでしょう。
やはり、リスクが高いものなので、身の守り方が第一にきてしまうのはしょうがないと思います。実際に危害が生じてからでは遅いですからね。しかし、AIというのは本当にワクワクする技術です。ちゃんと身を守りつつ、やっぱりワクワクしてこそ勉強の醍醐味だと思うので、そういった授業から行われていくといいですね。
素人考えながら、こんな教育現場があったらおもしろいな、と思うのは、簡単なAIアプリを開発してみる体験です。こちらは、最近登場したGoogleOpalから着想を得ました。プログラミングコード不要で、視覚的な操作で簡単なアプリ開発できるこちらのツールですが、このようなツールを安全性に特化したうえで、教育用のソフトとしてパッケージ化できたら、子供たちの創意工夫でAIの楽しさが伝わるような気がします。
いま、AIを学ぶというのは、教育業界に登場したばかりです。国もいろいろとワクワクする試みを画策中です。まだまだ始まったばかり、AI教育の前途が明るいことを願います、そして、自分もその一助に慣れたらこんなに嬉しいこともないと思います。