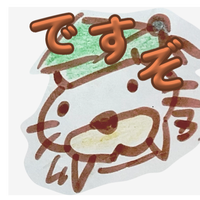こんにちは!
1級FP技能士のアシまるくんです。
第1章『数学嫌いの主観と現実』
突然ですが、クイズです!
『文系:49.9%、理系:25.7%』、これはいったい何の数字でしょうか?
さて、私には夢があります。夢と言っても、実現可能で成し遂げたい夢ではなく、"世界平和"くらいぼんやりとしたものですが、"数学嫌いの人が一人でも少ない世界"という夢です。それでまあ、厚かましくならない程度に、身の回りの人にささやかな普及活動(*1)を行っているのですが、少し意外なことに、最近出会う方は割と『数学に興味あって...』とおっしゃる方が多いのです。
そんな折、以下の記事に出会いました。
では、クイズの答えに戻りましょう!
記事によると、『理系科目が苦手だから文系に進学した割合が49.9%、かつ、選択理由の第1位』、『文系科目が苦手だから理系に進学した割合が25.7%』と記載されています。文理でおよそ2倍もの差が開いていることも驚きですが、文系の2人に1人が理系科目に苦手意識を持っていることは少し危機感すら感じる水準です。
ちなみに、『理系科目が嫌いだから文系に進学した割合が32.4%』、『文系科目が嫌いだから理系に進学した割合が20.3%』と苦手の時ほど、顕著ではありませんが、こちらも文理の差が見受けられます。
なお、私は、塾講師のアルバイト時代に、『"苦手・嫌い"を軸に文理選択を絶対するな!』と常々生徒に伝えていました。だって、大学に行けば当然勉強は難しくなるのに、"苦手・嫌い"で逃げた先も、"苦手・嫌い"になってしまったら、あなたの学生生活が暗く影を落としてしまうから。少なくとも生徒には明るい未来にいてほしい、というエゴイズムがありましたからね。
では、なぜこんな結果が生まれてしまうのか?ということを考察していこうと思います。
(*1)このブログの執筆ももちろんその一環です。E資格も1級FP技能士も、私にとっては、結局、数学の面白みを伝えるための手段の1つです。
第2章『負けて楽しいゲームなどない』
例えば、数学嫌いな中高生(かつて中高生だった方含む)に、なぜ嫌いなのかを尋ねてみると、"何の役に立つのかが分からない"と返答されるイメージが浮かんできませんか?
しかし、これはよくよく考えてみるとおかしな話で、1467年(人の世むなしい)応仁の乱を覚えてくださいと言われて、『将来何の役に立つかが分からないから、絶対に覚えたくないです!』と返してくる人がいたら、少し奇妙な感じがしますよね。
なので、"何の役に立つのかが分からない"というのは、ある種の建前とも言える、嫌いな本人自身すらも偽っているようなどこか本音ではない気がします。
では、何が彼ら彼女らをそんなに数学嫌いにさせているかというと、結局のところ、"できないから面白くない"というところが大きい(*2)と思います。
先ほどの応仁の乱の例に戻ると、別に鎌倉時代や室町時代の流れについてほとんど知らなくても、1467年応仁の乱は覚えることができますし、仮にもうちょっと深い知識や歴史的な流れを理解する必要があったとしても、奈良時代まで遡る必要はほぼほぼないと思います。一話完結型の知識とでもいうのでしょうか。
数学はそうもいきません。積み上げ型科目(*3)の女王ともいうべき存在で、一朝一夕で得点には結び付きません。さらに厄介なのは、暗記だけで得点に結びつくことはほぼないです。頑張って公式を覚えても、テストで得点をとれないのでは、面白くもないです。
数学の難しい問題を自力で解けた時の快感たるや何物にも代えがたいですが、そこまでの道のりはひどく険しいです。そんな思いをしてまで、何の役に立つのか分からないものをやりたくはない、というのがおそらく本音でしょう。
(*2)もちろん、特別な理由がある方はいると思います。例えば、クラスの数学が得意な奴がすごく嫌な奴だ、とか。虚数とかいう存在もしないものを考えるのがどうしても許せない、実際にあるものでもっと考えることがあるだろう、なんていう意見。先祖の仇が数学者だ、なんてこともあるやもしれません。三平方の定理を発見したピタゴラスですら、無理数の存在はかたくなに否定したそうですし、ノーベルも知人の数学者と折り合いが悪かったので、ノーベル数学賞を作らなかったり、と。数学嫌いな理由はいろいろとあるとは思います。
(*3)特に一部の幾何学は積み上げ型とは割と無縁だったりします。円周角とか、チェバ・メネラウスの定理とか。そういう一話完結型の数学もなくはないので、数学嫌いだけど、図形は好きだったなんていう話はちょいちょい聞いたりします。そんな唐突な感じが相容れず、私は高校までは幾何学はあまり好きではありませんでした。大学に入って多様体と出会い、『幾何学面白れぇ~』と思うようになりましたが、結局、確率解析を専攻しました笑
第3章『未来の子供たちと、かつて子供だった皆様へ』
では、"できないからつまらない"をなくすためには、どうすればいいでしょうか?
ここでは、2つのアプローチを考えてみましょう。一つは"できなくても楽しい"、具体的には、学んだことが役に立つことを実感してもらうことです。もう一つは、"できるようになる"こと(*4)ですね。
まず前者。以前の記事でも、国の指導要領だったり、共通テストの出題内容だったりで、なるべく実生活に寄り添うように工夫している、とお話ししました。
今回は国策から離れて少し別ベクトル、具体的には民間の立場からお話をしてみましょう。以下の本をご存じでしょうか?
こちらは渋滞学という、いかにも実生活で役に立ちます!という香りがプンプンしている応用数学の学問の第一人者である西成活裕先生が執筆されている人気シリーズの一冊です。
こちらの本が面白い点は、数学の言葉の作法について、『四の五の言わずに覚えろ』と言い切っていることや、動く点Pなどという得体のしれない演習問題が多く全国の中学生のやる気を削いできた2次方程式の問題について『猫用のトビラを作りたい』という極めてイメージしやすい問題に落とし込んでいるところです。
最近はこう言った良書も多いです。これらを相棒に、具体的な問題を解決する成功経験を積めば、分からないなりに面白い、と感じることができるのではないでしょうか?
ちなみに、私のおススメは、リボ払いの計算をやってみるのが実生活に登場する問題で1番面白いもの(*5)の1つだと思います。
そして後者。こちらも一冊の本を紹介したいと思います。
こちらは、医師・弁護士・公認会計士のトリプルライセンスで、まさにモンスター級の頭脳の持ち主である河野玄斗氏が最近出版された大学受験数学対策本です。彼は、『勉強はコスパ最強の遊びである』と常に掲げており、彼のYouTubeチャンネルでは、"大学2次数学RTA"というまさに、数学をゲームのように楽しむ動画も上げられています。
そんな彼が執筆したこちらの本は、まさに"受験ゲームの攻略本"。汎用性のあるパターンを具体例とともに紹介するという形式で、"この武器とると楽だよ"という内容が書かれています。もちろん、彼の優れた頭脳ありきで書かれているので、"そんな武器もらっても装備できない人も多いでしょ"なんてことも全く思わないわけではないですが、受験の攻略本という視点は面白いです。
真面目で潔癖な人であるほど、ズルしているようだとか、本当の学力が身につかない、とかいう反論もありそうですが、最初はそれでいいんじゃないかと私は思います。
問題を解いて、レベルが上がって、それで少し難易度の上がった問題を解いて、レベルが上がって、そうする間にちょっとずつ好きになってくる。好きまで行かなくても、嫌いではなくなってくる。やっぱり勝てるゲームは面白いですからね笑
今回は、数学嫌いを少なくするために、2つの書籍からヒントを得ました。
皆様のおススメの書籍があれば、ぜひ教えてください。
(*4)それができたら苦労しねえよ、という声が聞こえますが、そこを何とかしようぜ、というのが腕の見せ所です笑
(*5)この話をしたいがためだけに、1級FPを取得したといっても過言ではないくらい、金融講話をやるときの鉄板エピソードです。聴衆の皆様がいいリアクションをしてくれるのが毎回楽しみです笑