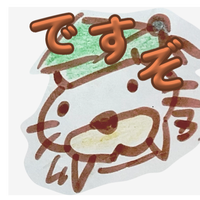こんにちは!
1級FP技能士のアシまるくんです!
第1章『ビジネス数学検定を語りたいんじゃ!』
さて、皆様はビジネス数学検定(*1)はご存じですか?
私自身、本屋に立ち寄るのが好きで、必ず数学書コーナーに足を運びます。最近、"ビジネス数学検定"の対策テキストをやたら見かけるようになりました。ビジネスに必要な「把握・分析・選択・予測・表現」の5つの数理的能力を測る検定です。
私は、数学科出身であることを公言しているので、いろんな場面で「数学の必要性は感じるんですが、いまさらどう勉強しようかな、という気持ちもあって...」といった世間話をいただきます。そんなとき、「最近は"ビジネス数学検定"なんてのもありますよ。」と返すのですが、ここである問題が浮上。それは、私のポリシーとして、"人に勧めるのに自分が内容を十分理解していないのはいかがなものか"と。
とはいえ、受験料も高い(*2)し、私のバックグラウンドでは取得しても特に箔はつかない。
『しかぁし!』
1級を90点以上で合格すると、三ツ星☆☆☆認定のオープンバッジがいただけるとのこと。というわけで、サクッと準備して96点/100点(*3)で三ツ星☆☆☆認定をいただきました。
その上で、G検定/E資格を取得できるほどの”数学リテラシー"がある方には不要な試験(*4)だな、と自信を持って言えるようになりました。今回は、このAI時代に求められる"数学リテラシー"が何か、を私の知識と経験を存分に活かして全2回に分けてしっかり考察していこうと思います。
(*1)"数検"でおなじみ日本数学検定協会が2006年12月から実施してます。意外と歴史がありますね。
(*2)2025年10月現在で、1級の受験料は8,800円です。
(*3)表計算ソフトが使える試験、かつ、使わないととても計算できない試験なので、基準統計量(単回帰分析の決定係数まで)がボタン一つで一瞬で計算できるマクロを3時間程度で作った以外は特に事前準備してません。唯一間違えた問題は、やたら説明変数が多くて、計算が大変な問題でした。
(*4)試験内容にニーズがあれば、別記事で解説します。
第2章『世はまさに大リテラシー時代』
さて、皆様は「〇〇リテラシー」という言葉をいくつ思いつきますか?
個人的よく聞くベスト3は、デジタルリテラシー・金融リテラシー(*5)・メディアリテラシーです。メディアリテラシーは、情報が氾濫する現代に情報を適切に取捨選択して、責任ある判断をするためのものなので、デジタルリテラシーのお仲間さんですね。
そんなわけで、現代で身に着けるべき2大巨頭は、"デジタルリテラシー"&"金融リテラシー"でしょう。デジタルリテラシーに関しては、私のような若輩者より諸先輩方たる皆様の方がお詳しいと思いますので、金融リテラシーについて、少々解説いたします。
金融リテラシーは、”国民一人ひとりが、より自立的で安心かつ豊かな生活を実現するため”に身に着けるべきものとされており、日本における金融教育を一層推進するために、2024年4月にJ-FLEC(金融経済教育推進機構)が立ち上げられました。高校生の家庭科の教科書に"金融教育"が追加されたというニュースを1~2年ほど前に耳にされた方もいらっしゃるかと思います。また、"金融リテラシー・マップ"なるものも公開されています。
デジタルリテラシー同様に公的・民間問わず、非常に多くの教材が溢れかえっています。
金融リテラシー・マップをきわめてざっくり紹介すると、「適切な家計管理ができるか」、「ライフプランを設計し、将来を見据えて貯蓄・運用ができるか」、「金融に関する商品や制度を理解しているか」、「トラブルに巻き込まれたとき、適切に相談できるか」の4つのパートに分かれます。
ここで、あることに気づきますね。"ん?数字にある程度強くないとまずくない?"と。デジタルリテラシーの中に、"数字・数学に強いこと"が含まれるのは、ご存じのことかと思いますが、金融リテラシーも同じなのです。つまり、現代の2大巨頭リテラシーを身に着けるために、"数学リテラシー"を身に着けることは避けては通れません。
(*5)『お前、1級FP技能士を自己紹介に入れる割に、全然お金の話しないよな笑』とお思いの皆様、お待たせいたしました!ついに金融に関してお話しさせていただきます。
第3章『いまの10代が身に着けてくる数学リテラシー』
さて、いよいよ本丸たる数学リテラシーについて話を進めていきましょう。
まず、今年の2月に、文部科学省から高校の数学教育のための資料として、"数学的リテラシーを育む授業事例集"なる資料が公開されています。
こちらの資料では、"OECD生徒の学習到達度調査(PISA)2022年調査国際結果報告書"における規定を用いて、数学的リテラシーを以下の通り、定めています。
数学的に推論し,現実世界の様々な文脈の中で問題を解決するために数学を定式化し,活用し,解釈する個人の能力のことである。それは,事象を記述,説明,予測するために数学的な概念,手順,事実,ツールを使うことを含む。
この能力は,現実社会において数学が果たす役割に精通し,建設的で積極的かつ思慮深い21世紀の市民に求められる,十分な根拠に基づく判断や意思決定をする助けとなるものである。
このようなリテラシーを身に着けるための授業事例として、現実で起こりうるシチュエーションを用いた問題や楽しく学ぶゲームを取り入れることが紹介されています。
このような動きは、直近で聞いたことがありますね。そうです、センター試験から共通テスト(*6)への移行です。"数学の問題を速く正確に解く能力"を求められる従来のセンター試験から、"現実的な問題に対し、適切に文章を読み解き、数式を用いて解決する能力"を求められる共通テストへ2021年から変わりました。AI時代を生き抜くためのより実践的な科目として、"情報I"が2025年度から共通テストに導入されたのは記憶に新しいかと思います。
以上の動きから、より実践的な数式を使う力がこれからの時代に求められていることを感じることができます。
(*6)私は数学の能力を衰えさせない目的で、毎年共通テストの問題を制限時間内に解くようにしています。実感としては、まず、明らかに時間が足りない。そして、計算量も多く、電卓なしで解ききるには相応に計算力も必要だと感じます。数学科卒のプライドを懸けて、ほとんどの年で90点以上をキープしていますが、たまに下回るのも事実...
第3.5章『次回予告!』
ここまで時代の流れを語ったので、後編では、"私の考える数学リテラシー"について述べたいと思います。具体的には、①算数とは何かを考える、②数学を「計算・言語・証明」の3要素に分解する、③立場によって求められる数学リテラシーの階層、の3つを主軸に語りたいと思います。
前編だけでも結構なボリュームになりましたが、後編もお付き合いいただけると大変嬉しいです。