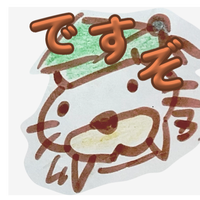こんにちは!
1級FP技能士のアシまるくんです!
第0章『仕事はお好きですか?』
さて、皆様、仕事はお好きですか?
私は嫌いです笑
仕事そのものにやりがいを感じる方も、仕事は嫌いだが職場の人間関係が好きだという方も、仕事は嫌いだがその無駄をなくす作業には情熱が湧いてくるという方も、大切な家族のために嫌いな仕事も頑張るんやという方も、推し活の活動資金としか思っていないという方も、仕事が嫌いすぎて人生が憂鬱だという方も、もうFIREしてやって悠々自適な生活だぜぇ~という方も、100人いれば100通りの答えがある質問かと思います。
さて、どんな考え方を持っているとしても、仕事とは"他者の問題を解決する代わりに報酬をいただく"ものだと私は考えています。この"問題の解決"に照準を合わせたとき、"分かる"の前に"知る"が来るという定説が浮かび上がります。
本当にそうでしょうか?私なりの立場で、議論をしてみたいと思います。
第1章『仕事脳の優秀なあなたへ』
さて、仕事において、"知る"ということはすべての始まりであるような気がします。
例えば、名刺交換。これは仕事を始める前に、相手に自分を"知ってもらう"ための手段です。仮に社内であっても、初めて仕事をする方とは、自己紹介から始めますね。問題解決のために尽力する(予定の)自分のことをまず知ってもらいます。
また、企業が広告宣伝のために多額を費やすのも、"知ってもらう"ことが目的です。問題解決のための商品・サービスを提供するために、まずはその製品・サービスを知ってもらうことに力を注ぎます。
では、自身が問題解決のために、どうしているかを考えてみましょう。
上記の記事が分かりやすいです。"知る"とは単に自分の頭の中にあること、"分かる"とは頭の中にあることを分解してその構造を掴んでいることを指します。
なるほど、こういう風に言われると、"知る"は"分かる"の前段階だと言われても、納得してしまいそうな気がします。 仕事という問題解決の場においては、確かに、"知る"が"分かる"の前段階に来そうです。
第2章『僕らの世界は意外と曖昧に回っている』
さて、"知っている"という言葉は意外と曖昧です。(*1)
例えば、『総務部の遠藤さんって知ってる?』と聞かれたときに、社内に見かけたことがあり、存在を認識していれば、答えは『知っている』でしょう。
同じく、『今度、うちの部門の執行役員に就任する田中さんって知ってる?』と聞かれたときに、『田中さんは理系畑の人で、初めはシステム系配属だったけど、30歳直前で急に営業に回されたんだよね。その頃にご結婚されたこともあって、慣れない営業畑で頑張って40歳目前で課長昇進。その後、50歳手前で、子会社に在籍出向を条件に部長職に昇進して、そこで製造現場のことも経験されたみたい。で、今回、本社に戻ると同時に執行役員に就任するらしいよ。』でも、答えは『知っている』です。
"知識の濃度"とでもいうのでしょうか。深い知識は、時に"分かる"を凌駕します。
また、知っているだけでよく分かっていなくてもできてしまうことはたくさんあります。スマホなんていい例です。簡単な使い方さえ知っていれば、その実よく分かっていなくともツールとしてまあそれなりに使えている人が大半だと思います。
そして、もう一つ。"知らなくても分かる"ことが世の中には意外とあります。
行政手続きはいい例です。行政手続きについて、いちいち覚えていないことの方が多い、と思います。しかし、多かれ少なかれ苦労はあれど説明を聞きながら進めて完遂できると思います。そして、基本その場限りのことなので、手続きが終われば頭からは遅かれ早かれその内容は消える人の方が多いと思います。つまり、手続きについて"知る"ことはないが、説明が"分かる"から可能なことですね。このように、"知識"として持ち合わせなくても、その場限りの"理解"で乗り切る場面は意外とあります。
このことから、私は、"知る"は"分かる"の前段階ではなく、相互補完の関係であると考えます。"知識"が"理解"を助け、"理解"はさらなる"知識"を呼ぶ。両輪と呼ぶにふさわしい関係だと考えています。
(*1)もちろん"分かる"という言葉も曖昧です。その上、"分かる"は"分かったフリ"という自分自身をもだます行為に直結しやすいです。しかし、"分かる"という言葉には、自分自身が納得できるというニュアンスを含みます。
第3章『数学という名の異世界へようこそ』
さて、最後に数学という学問の特異性について触れて終わりましょう。
以前の記事で、私は数学リテラシーの習熟レベルの最低は"分かる"だと述べました。これは前章の通り、"知る"と"分かる"を明確に別物と考えていることもありますが、もう一つ、数学という学問の特異性があります。
皆様は、『数学者は、1+1=2にも、膨大な証明を要する。』という話を聞いたことがありませんか?実際問題その通り(*2)で、"1+1=2"なんていう小学1年生(もしかしたら幼稚園・保育園の子)でも分かるような単純な計算ですが、"そもそも1とはなんなんだ"、"2っていったいなにもの?"、”+ってなに?”など、この短い問題でも厳密に考え出すと考えることがいっぱいです。
このことから分かる通り、数学とは"本当に0から議論を積み上げていく学問"なのです。"知らないフリゲーム"とでもいうのでしょうか?今、正しいと分かっている情報だけから、新たに正しい情報を見つけ出していく過程なのです。極論を言ってしまうと、数学を突き詰めていったときに、"知る"という過程が重要ではなくなるんですよね。
そういった理由から、数学を学ぶときは"知識"から入らずに"理解"から入る。覚えるのではなく、説明を聞きながら(見ながら)理解する。そういう姿勢が数学リテラシーの向上につながります。
とはいえ、普段使いの数学(*3)の立ち位置から言うと、登場頻度の高い共通認識のような概念があるので、そういうものを"知る"ことは"分かる"助けにはなります。なので、覚えても意味ないよ、とまでは言いません。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
皆様の数学ライフに幸多きことをお祈り申し上げます。
(*2)もちろん普段からこんなしち面倒くさいことを考えているわけではありませんが、本当に真剣に数学研究に向き合うときは、このような態度で取り組みます。
(*3)普段使いの数学ってなんやねん、と我ながら思いますが、よく登場する概念e^xとかそういうものですね。