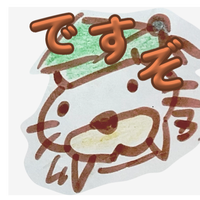はじめに
会議や交渉の場で、誰かがあえて冗談を言ったり、空気を和ませたりすることがあります。本人の意図は「緊張を和らげる」「議論を停滞させない」「誰かが言いにくいことを軽く投げる」など様々ですが、この役割はしばしば「道化」と呼ばれます。
AIが発言や手続きを支える時代になりつつありますが、この道化を演じる行為はどうでしょうか?
個人的には、なお人間にしかできないものとして一部残りそうですが、AIと道化の役割は親和性が案外高く、補い合う可能性もあると思います。
本稿では、AIと道化の関係を考察します。
第1章 道化の本質とは何か
道化とは、単なる「冗談」ではありません。
・緊張した場を和らげる
・笑いを通じて沈黙を破る
・意見を言いやすい雰囲気を作る
・本音を引き出すために外れ役を買う
上3つはアイスブレイクとも呼ばれるかと思います。
つまり道化は「場の空気を調整する媒介役」です。これはルール化できない空気の読み方に直結しており、組織運営に欠かせないものです。
ピョートル・フェリクス・グジバチ氏が書いた『世界の一流は「雑談」で何を話しているのか』においては、著者自身が日本においては外国人として扱われるという「外国人カード」を活かして、あえて聞きづらい内容に単刀直入に踏み込む役割を果たしていたというエピソードが記されています。
日本人がそのまま同じことをやっても、同じ効果は得られないでしょう。
第2章 AIの強みと道化の接点
AIは、人間ほど空気を読めませんが、次の点で「道化的な役割」と親和性があります。
・突飛な発言をする
・失敗を恐れない
・AIそのものも含め、公平に外れ役を担える
・再現性をある程度プロンプトで制限できる
特に、私自身は4つめの再現性に強みがあると感じます。
プロンプトの厳密な制御により、一定のパフォーマンスを確保できるのは非常に有用ですし、AIは「意図せず道化を演じる」ことが自然にできる存在です。
《参考》
===========================================================
AIによるハルシネーションをプロンプトの制御で抑えつつ、人間の道徳について倫理的に掘り下げた興味深い記事です。ぜひご一読ください。
===========================================================
第3章 人間にしかできない道化の演じ方
一方で、AIが真似できない道化の要素もあります。
・タイミング感覚:場が張りつめた瞬間にあえて冗談を差し込む。
・関係性の調整:上司や取引先の機嫌を読みつつ、人によって可変するラインを探る。
・責任の引き受け:場を壊したとき、本人が「冗談でした」と責任を引き取る。
AIには責任も人間関係もないため、道化のリスクを引き受ける部分は担えません。リスクテイクは人間の責任であり、特権なのです。
第4章 AIと人間が共演する道化のデザイン
ではどうすればよいか。道化は人間が担い、AIは補助的に外れ値や奇抜な発想を提供する設計が現実的ではないでしょうか。
会議でAIに一番突拍子もない選択肢を提示させ、さすがに○○は突飛すぎるというところから、現実的な落としどころの議論のきっかけにするという流れですね。
優れたチームにおいてはメンバーの役割は決まっており、相補的に活躍しますが、そのうちの再現しやすい道化の一部をAIに委任する形です。
つまり、人間とAIが「二人羽織の道化」を演じる形です。人間は空気を見て責任を取る、AIは突飛な発想を担う。この組み合わせが最も親和性が高いのではないでしょうか。
おわりに
AIは圧倒的な情報量から様々なものを提供する一方で、しばしば外れ値を生みます。それを笑いや軽さに変えるのは、人間が持つ「道化の技」です。AIは場の補助役として意図せず道化を演じ、人間は責任を持って意図的に道化を演じる。この共演こそが、AI時代における組織や会議の新しいデザインになるでしょう。
「AIが言うなら仕方ない」として受容されていくのか、「AIにあんなこと出力させんなよ」になるのか、「言いづらいことAIに言わせただけじゃねえか」になっていくのか、受け入れる側の人間がどの程度親和していくのでしょうか。まだまだ未知数です。