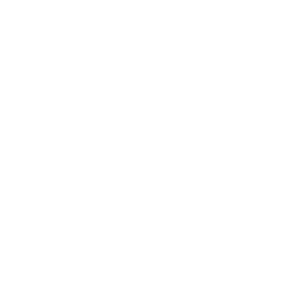本稿のきっかけ - ワークショップがうまくいくときってどういうときだろう?
筆者はここ数年、ワークショップ型のAI教育プログラム策定に関わることが増えています。ワークショップ型というのはここでは、1〜2時間で学ぶ講義やハンズオンではなく、終日もしくは2〜3日集合し、集中的に学ぶ場のことを指しています。
このタイプの教育プログラムがうまくいくときって、ある種のいくつかの要因が揃ったときだなぁ、そこには共通性があるなぁ、それらはLTや1〜2時間の講義・ハンズオンが成功する際の要因とはちょっと違うなぁ、というのを以前から感じていました。
そんなとき、現在のキッザニア副社長の宮本美佐さんに、青山学院大学で「ワークショップデザイナー育成プログラム」なるものを学んできたという話を聞きまして大変興味を持ち、いろいろ勉強を始めました。
本稿では、それを通じて学んだこと(の途中経過)を紹介したいと思います。
ワークショップとは何か?
ワークショップの元来の意味を英英辞典(*)で調べると以下のようになっています。
a room or building where tools and machines are used for making or repairing things.
(*) Longman Dictionary of Contemporary English で調査
日本語で示すならば「修理工房」という感じでしょうか?日本にせよ欧米にせよ、ワークショップというのは、伝統的な技術を発揮して職人が何かを作り出したり修理する「空間(space)」という感じがします。ちなみにフランス語だと「atelier」というそうで、なんか素敵な感じです。
これが転じて、我々がデザインしたい所謂ワークショップに近い定義も英英辞典に記載されていました。
a meeting at which people try to improve their skills by discussing their experiences and doing practical exercises.
日本語で示すならば「場」ですかね?「場」というのはちょっと深遠な意味があり、場所だけではなく時間も共有するという意味での「場」という意味を想起させます。そして後半の「議論して実際にやってみる」というのが現在の多くのワークショップで行われていることそのものなんだと思いました。
ワークショップ7つの特徴
経験学習(experiental learning)の研究者として著名なBrooks-Harris. J. EおよびStock-Ward.S.Rは、著書「Workshops: Designing and Facilitating Experiental Learning」(1999)にて、ワークショップには以下の特徴がある、と述べています。(カッコ内は筆者意訳です)
- Short-Term Intensive Learning (短期間での集中学習)
- Small Group Interactive (小グループ内の相互作用)
- Active Involvement (積極的関与・巻き込み)
- Development of Competence (コンピテンスの開発)
- Problem Solving (問題解決)
- Behavior Change as an Outcome (成果(の一つ)としての行動変容)
- Application of New Learning (新たに学んだことを実場面へ)
確かに、1〜2時間ではなく終日もしくは複数日時間を掛けるワークショップは「経験学習」の形をとることが多く、その本質が上記に詰まっている気がしました。
ワークショップのステークホルダー
前述のBrooksとStock-Wardは、同書の中でワークショップのステークホルダーについても述べています。
- コアメンバー, 運営協力者
- ワークショップ参加者
- (ワークショップ参加者が所属する)関心共同体(=告知対象者)
- クライアント
- スーパーバイザー
- 研究者
このモデルは、ワークショップ参加者と運営コアメンバー、および周囲の関係者がどのようにインタラクションを行うかをも想起させます。
ワークショップのコンセプト
山内祐平、森玲奈、安斎勇樹は著書「ワークショップデザイン論 - 創ることで学ぶ」の中で、ワークショップのコンセプトを以下のフレームワークで表現しておられます。
「⚪︎⚪︎を創ることで、◻︎◻︎を学ぶ」
これは正直、なるほど、と思いました!⚪︎⚪︎が活動目標となり、◻︎◻︎が学習目標となります。
正直、筆者がこれまで実施してきた、終日もしくは複数日に渡って行う多くの技術系セミナーの大半はこの形で表現できるんですよね。AIの教育プログラムもしかり、です。
ワークショップのプログラムモデル
「創ることで学ぶ」がワークショップのコンセプトだとすると、ワークショップのプログラムには創る活動を含んでおくことが非常に重要となります。
最近の技術系のセミナーではよく「ハンズオン」という言い方が使われますが、ハンズオンは比較的「レールが敷かれている経験学習」という感じで、自由度が低め(だがその代わり短時間で習得可能)。
これに対し「創る活動」というのは意図的に自由度を高めに設定してあって、だから途中で「どうすればいいんだろう?」と悩んだりしながらもそれを解決していくことで深く学んでいくというイメージになります。
それらを踏まえ、前述の山内・森・安斎は、同書の中でワークショップのプログラムモデルを以下のように述べておられます。
導入 → 知る活動 → 創る活動 → まとめ
学習を促すことのできるワークショップとするための要件
山内・森・安斎は更に、同書の中で、学習を促すことのできる要件として以下を挙げておられます。
◾️学習を生起する企画の要件
楽しさ
葛藤と矛盾
リフレクション
実践者にとっての実験
余白のある設計
これらも本当にその通りだな、という感じなんですよね。何はともあれ「楽しさ」があって、だけど「創る」課題がちょっと難しくて悩んだり、フィードバックがあったり、参加者がちょっと実験できたり、そのための余白があったり・・・
成功したときって確かにこれらが全部備わってたなぁ、と強く思った筆者なのでした。
まとめ
こうして学んだことをまとめて、過去作ったAI教育プログラムを振り返ると、なんでそれらがうまくいったのか凄くよくわかる気がしました。
経験学習としてのワークショップ、という切り口でもう少しまとめることが残ってそうですね。
今後ですが、もしも許諾が得られれば、今まで策定したAIの教育プログラムを上記のフレームワークで振り返り、その良さを表現してみたいな、とも思います。